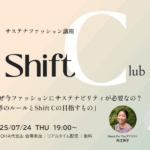Contents
私たちの手放した服は、世界のどこかで役立っている?
ファッション業界における「サステナブルな取り組み」として多くの人が真っ先に思いつくのは、この数年でごく一般的になった「不要な衣類の回収ボックス」の存在だ。まだ十分着用可能だがなんとなく飽きてしまった服も、メーカーから「リサイクルしますよ」と言ってもらえたら罪悪感なく手放せるし、きっと「どこか」で役立ってくれているはず……回収ボックスを使う人に共通する意識はそんなところだろう。だがその「どこか=最終到達地」は一体どこなのか――それについて考えたことがある人はそう多くはないだろう。パリのオートクチュール・コレクションで唯一の日本人デザイナーであり、環境負荷の低減を意識しながら「理想の服作り」を模索してきた中里唯馬は、そんな数少ない一人だ。「作られ使われた衣服が最終的にどうなるのかを知れば、デザインがどうあるべきかが自ずと見えてくるのではないか」。2023年のコレクションを前にそんなふうに考えた中里は、インスピレーションを求めて「衣服の最終到達地=ケニア」へと向かう。

古着市場の先にあった「最後の場所」
映画は前半、彼のケニアへの旅に同行し、想像を絶する状況に言葉を失ってゆく中里の表情を映し出す。
まず彼が訪れたのはケニアの首都ナイロビにある巨大な古着市場ギコンバ。市場はその入口で中里自身が「ここに入るのか」と慄くほどの混沌である。次々とやってくる巨大なコンテナの中には、まるで「ハム」のようにビニールと荷物ヒモでぐるぐると括られた、一辺1~1.5m程度の直方体がぎっしり詰まっている。「ミツンバ」と呼ばれるその直方体は、大きなビニール袋に真空パックさながらに、無分別のあらゆる衣類をぎゅうぎゅうに詰めたものだ。市場にはその場で古着のサイズ直しなどを請け負う人々も多く、その作業過程で出た切れ端によって地面が埋め尽くされている。だがここは「衣服の最終到達地」ではない。こうしたリサイクルにさえ値しない粗悪な衣類が、さらに運ばれていく場所が最終到達地=ゴミ埋立地のダンドラである。巨大なアフリカハゲコウが群れをなして飛ぶその場所には、衣類を含めた10万トンものゴミが巨大な台地を作っている。マスク姿の中里が時おり咳き込むのは、ところどころで上がる煙と異臭のためだ。町を流れる川には捨てられた衣類が流れ出し、その繊維がやがてはマイクロプラスチックとなって海へと拡散し、生態系を破壊している。「ミツンバ」という名目で欧米やアジアからケニアに輸出される廃棄物は、年間16万トンにも及ぶ。実のところこうした場所はケニアのみならず、インド、カンボジア、チリなど、世界中に点在している。ファッション業界におけるサステナブルは、生産過程のフェアトレードや農薬などの使用の有無、製造過程に使われる化学物質や水の量、リサイクル可能な素材か否かなどで語られることが多いが、実のところ最も大きな――そして最も語られることのない問題は「年間に兆単位で作られる服の85%が廃棄されている」という現実なのかもしれない。

これ以上服を作ることは「罪」なのか?
ケニアで話を聞いたすべての人たち――ゴミ捨て場で生きる人達、市場で古着を売る人たち、古着の過剰供給により瀕死の状況にあるケニアのファッション業界の人たち――に「もう服を作らないでくれ」と言われた中里の葛藤、自己矛盾、罪悪感は、想像に固くない。強く印象に残ったのは、中里が「粗悪な衣服」と知りながら、パリ・コレクションで使う素材として「ミツンバ」を150kgも買って帰ったことだ。正直を言えば「そんなに買って大丈夫なのだろうか?」とヒヤヒヤしたのだが、それは裏を返せば、彼が目の当たりにしたケニアの惨状に強く打たれた証左でもある。だがケニアでの体験によって導き出された彼の思いや葛藤は、ケニアを見ていないチームにはなかなか伝わらない。帰国後の会議はやんわりとした拒絶反応に包まれる。映画がそこに示すのは、知見の差により、関心の違いにより生まれてしまう社会の断絶、その縮図でもある。

ゴミの山からドレスを作るオートクチュール・コレクションの挑戦
用意されたプランを変更して始まったコレクションは、さらに様々な不測のトラブルにも見舞われ、これまでにないほどの難産に。そういう中で苦しみながら中里は「現時点での落とし所」を探ってゆく。つまるところチームのメンバーの戸惑いは「ビジネス拡大のためのコレクションで、ビジネス拡大に警鐘を鳴らすメッセージを発する」という矛盾にある。だが複雑に絡み合った現代社会において「矛盾すること」を理由に諦めていたら、問題は何一つ解決しないし、前向きな未来には繋がらない。ビジネスと環境の矛盾をどのバランスで両立させていくか――それこそが課題なのだと映画は教える。

トップを走る者の責任として「旗と立てていく」
もちろんこうした動きには反発はつきものだ。人々は既成概念や「今までのやり方」を捨てることを嫌がり、対抗する価値観を受け入れることを「割りを食った」と感じるものだ。これまでと異なる動きは時間もリソースも余計に奪われる。映画には描かれてはいないが、道は茨だらけに違いない。ファッション業界のトップにいる中里がそういう道をあえて選び、ノブレス・オブリージュとも言える行動を起こしたことに感動する。そうした行動に出る「トップにいる人」を久しく見てこなかったからかもしれない。映画を見た後は、多くの人が自身の消費行動について考えさせられるだろう。ポリエステル混の服は買うまいと思う人も少なからずいるかもしれない。矛盾を抱えながらも、パリコレと言う世界的な舞台において「まずは旗を立てること」には、必ずや意味があるはずだ。
『燃えるドレスを紡いで』
K’s cinema、シネクイント他全国順次公開中